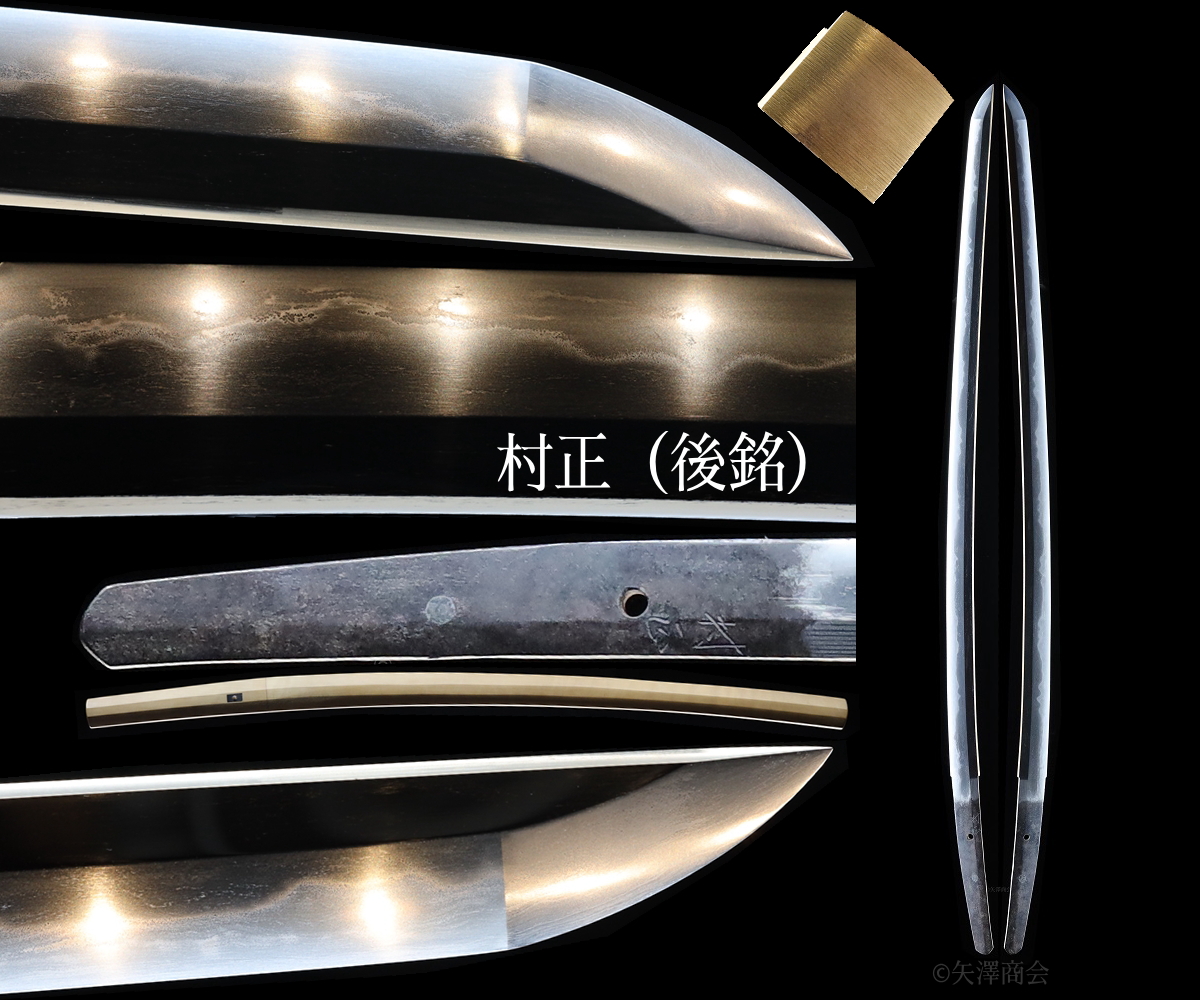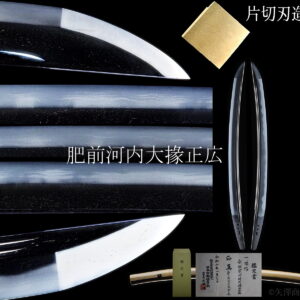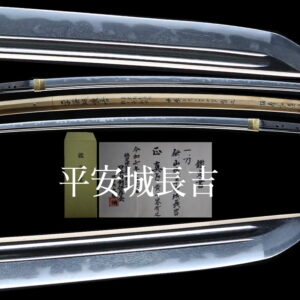説明
ここに画像が表示されます。(通信環境により数十秒ほどかかる場合もございます。)
1/3

ここに画像が表示されます。(通信環境により数十秒ほどかかる場合もございます。)
2/3

ここに画像が表示されます。(通信環境により数十秒ほどかかる場合もございます。)
3/3
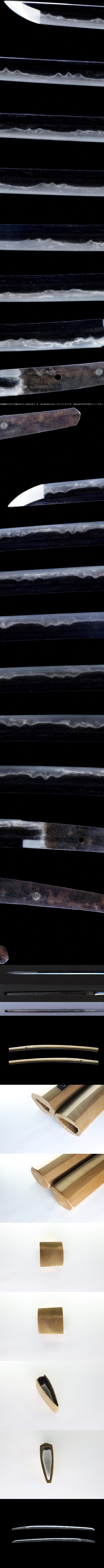
委託販売
村正
村正について
村正は千子村正を始祖とする伊勢国桑名で活躍した刀工での一派で、妖刀村正と名高い。
日本刀名鑑には古刀期に四人(現存する刀剣)、現存しない刀剣含めると八項、新刀期には三項(慶長、寛永、寛文)記載あり。
その鋭い切れ味や表裏揃う刃文は当時から需要があるも、江戸時代になると、家康の祖父清康と父広忠が暗殺された時に村正の刀が用いられたり、
長男の信康が切腹させられた際の介錯に村正が用いられたりした経緯から、村正は徳川家で忌み嫌われたことにより、処分されたり、銘が削り取られたと言われている。
本刀、銘が消され、後銘を入れられた形跡あり、刀身重量感、姿から古刀ではなく、新古境、江戸初期寄りに見受けられます。
勉強不足で固定観念から村正=室町後期というイメージが強く、出品前まで悩んでいたところがあったのですが、資料等を見ていると、新刀期にも村正はいるとのこと
少しづつ夢がでてくるではないですか。
淡く映りがたち匂口締り、刃冴える
刀剣学では新古境ははっきり作風がわかれず混在すると言われております。
銘を隠し刀身を観れば良く切れそうな良い刀、銘を見れば云われ通りの怪しい妖刀
表裏揃う刃文
関の特徴がでており、折れず曲らず良く切れる実用的な機能美が見え隠れする御刀でございます。
一概に悪意のある偽銘とは言えない、後銘村正なのであります。
新刀期の村正が作刀し、後に後銘が入れられた刀なのかもしれないのです。
残念ながら現状の規定ではこういう後銘は保存、正真鑑定が付かないのですが、経験上、無銘ならば刀身状態良いため保存以上で合格します。
本刀、刀剣鑑賞、拵に入れれば居合、物斬り全てに対応できる一振りと存じ上げますが、約400年程前の刀剣と見受けられ、物斬りは勿体ないのでおすすめしません。
白鞘入り
無鑑現状販売
日本刀は日本の有形文化財でございます。
私たちが後世に残すべき大切な文化財です。
後世にかけて大切にしてくださる方のみご所有ください。
次の主が見つかるまでの間、一時的に弊社にてお預かりし、お世話をさせていただいております。
刀剣のお買取り、下取販売、仲介も承っております。
刀が貴方をお待ちしております。
商品の状態
*刃切れ・刃絡み・刃こぼれ・曲がり・撓え・膨れ・匂い切れ・駆け出しなどございません。
*時代による、汚れ、細かな擦れ傷,劣化等はご了承ください。写真を参考にしてください。