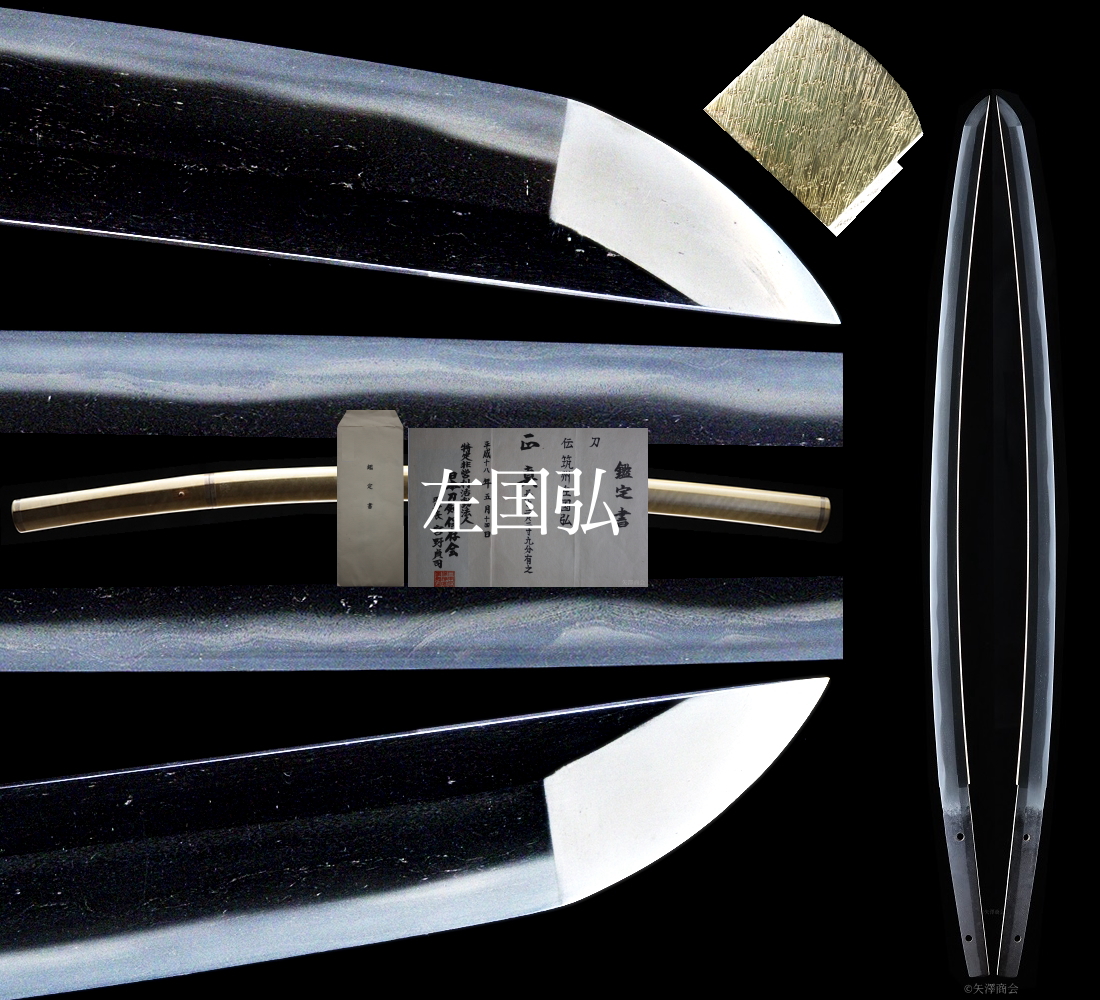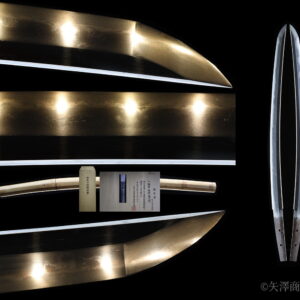説明
ここに画像が表示されます。(通信環境により数十秒ほどかかる場合もございます。)
1/3

ここに画像が表示されます。(通信環境により数十秒ほどかかる場合もございます。)
2/3

ここに画像が表示されます。(通信環境により数十秒ほどかかる場合もございます。)
3/3
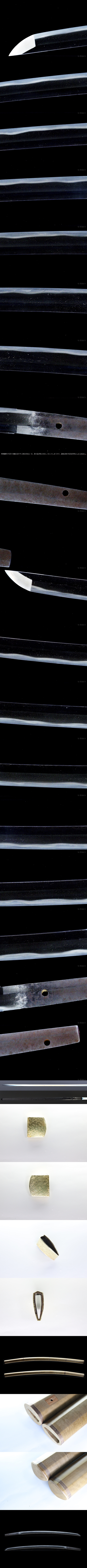
地刃美しく重要刀剣級の出来
本刀、筑前左国弘と極められ刃長二尺三寸弱
大磨り上げでこの長さのため元太刀として作刀されたことは容易に推測ができます。
時代は正平(しょうへい)西暦でいうと1346年から1370年までの期間の元号
筑前国左文字は、正宗十哲の一人に数えられ、正宗の相州伝を習得した刀工として名高い。
南北朝時代初期に出現し、それまでの古典的な九州物の作域から脱却し、旧来の西海道諸鍛冶とは全く違う作域を樹立、刃は明るく冴え、垢抜けした独自の作風を創出する。
一門の安吉・行弘・吉貞・国弘・弘行・弘安らは師伝をよく継承して大いに活躍する。
国弘は吉弘の子、また一説には定行の子とも伝えられ、有銘の現存作は少ないが短刀に正平十二年紀のものあり。
商品の状態
*刃切れ・刃絡み・目立った刃こぼれ・曲がり・撓え・膨れ・匂い切れ・駆け出しなどございません。
*時代による、汚れ、細かな擦れ傷,劣化等はご了承ください。写真を参考にしてください。